2025.10.23 Thu
学会デビュー1年生の“プライマリ・ケア”体験記
第15回日本プライマリ・ケア連合学会 東北ブロック支部学術集会に参加して

今回この学会に参加したことで、以前よりもプライマリ・ケアや総合診療医についてイメージが湧くようになった。以前は「プライマリ・ケア」は単に初期診療のことだと認識しており、その重要性はわかるものの、なぜ特に「地域医療」において重要なのかわからなかった。しかし、今回の学会に参加して、「プライマリ・ケア」は多職種と地域資源がネットワークを形成し、身近で継続的かつ包括的なケアを提供するシステムのことだと学んだ。
そしてその対象は患者だけでなくその家族にもあり、患者の疾病だけでなく、「病い」を治療する目的があると知った。このことを踏まえると「プライマリ・ケア」が特に「地域医療」において重要である理由がはっきりとわかった。それは、患者が心身共に健康でいられるサポートをする上で、地域医療の場は患者の抱える「病い」を取り除くことができるからである。ご講演頂いた松岡文彦先生は、医学的解釈における病気を「疾病」、本人の解釈における病気を「病い」というように区別していた。この言葉をお借りすると、急性期病院で治療を受ける時、多くが命に関わる重大な病気を抱えており、まずはいち早くその病気(疾病)を治さなくてはならない。一方、地域医療の拠点である亜急性期病院や回復期病院では医学的解釈における病気(疾病)に限らず、患者が感じる苦しみそのもの(病い)を取り除くことに焦点を当てることができる。患者が心身共に健康でいられるようにサポートすることを目的とするなら、治療の対象を「疾病」に限定する必要はなく、「病い」にまで広げてサポートする方が、より目的達成に近づくのである。
また、この「プライマリ・ケア」の主な担い手が総合診療医である。これまで「疾病」の治療に重きを置いてきたが、これからは「病い」の治療の重要性をもっと認識し、「プライマリ・ケア」ができる環境の整備が必要である。そのような環境を整備するために、ご講演頂いた前野哲博先生は、急性期病院を集約し、亜急性期病院や回復期病院を各地に整備することで、持続可能性を維持しつつ、医療の質を出来るだけ落とさない工夫をして、人々の心身の健康をサポートする仕組みを整えていくことになると想定されていた。総合診療医は、亜急性期病院や回復期病院を中心にその仕組みを支えていく役割がある。この役割は今後一層重要視されていくと思われる。その点で、総合診療科は将来に渡って専門性を維持しやすい診療科であると感じた。これらのことから、総合診療医は単にどんな症状や病気でも診る医師でなく、医療を面で支えるためにリーダーシップを発揮してプライマリ・ケアを担い、患者の健康をサポートする医師であるとわかった。
また、2日目に参加した「玄関からの気づき〜玄関診断学のすすめ〜」というワークショップでは、訪問診療において玄関から患者の家庭環境やADLの程度、趣味嗜好などがわかるということを学んだ。これらをコミュニケーションに活かして患者との信頼関係の構築に繋げたり、患者の健康をサポートするための糸口を探す手掛かりにするなど、何気ない情報にも重要な手掛かりがあると知った。このように、患者の病気とは少し離れたことまでよく知るということが「プライマリ・ケア」に重要だとわかった。
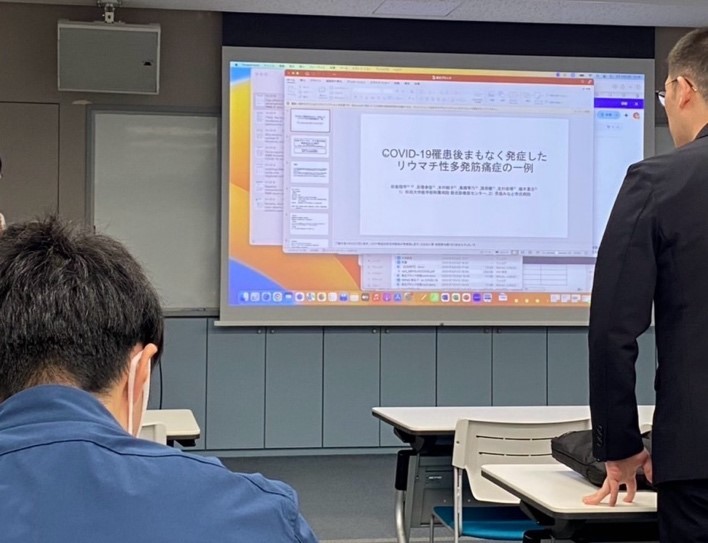
今回の学会を経て、総合診療医への理解が深まったと感じた。改めて総合診療医の具体的なイメージをしてみると、総合診療医の役割は小学校教諭に似ていると感じた。小学校教諭は、単に全教科教えるのではなく児童一人一人の性格や家庭環境等の彼らを取り巻く環境まで考慮し、健やかに成長できるようにサポートする。各教科に対しての専門性は高くなくても、児童の成長には欠かせない重要な役割がある。
総合診療医は専門性が高くないという評価を受けると聞くが、小学校教諭のようにその重要性がもっと認められていってほしいと思う。また、総合診療医に限らず、地域医療を担う医師には高い総合診療レベルが求められているということを忘れずに、今後も広い視野を持った医師になるために学習を続けていきたい。










